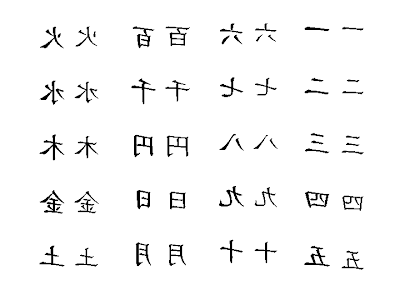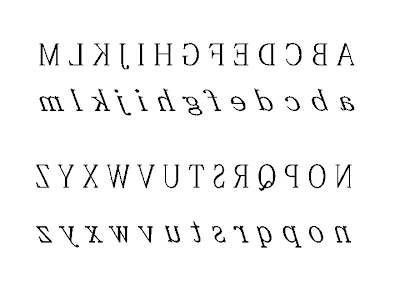〈なぜ右文字はよくないのか〉
そこで左利きの人間にとって、なぜ現状の文字(右文字という)を書くのが不都合なのか。おもに左手で書く場合だが、右手で書く場合も裏返しで同じような不都合がある。
具体的には、次のような点があげられる。
第一に、左利きは、漢字を上手く書くことができない。ひらがなも漢字も右手で書くようにできているからだ。ときどき左利きの人が腕をくねらせて字を書いているのを見かけるが、あれは何をしているかといえば、肘を九〇度曲げ、手首を九〇度曲げ、一八〇度回転させて、左手を右手のポジションに持ってきている。左手で擬似右手を作っているのだ。あの窮屈さできれいな字を書くことはできないし、傍目にも見やすいものではない。
またときに、左利きにもかかわらず、サラサラと滑らかな様子で書いているのを見かけることもある。しかしたいていの場合書かれた文字を見ると形の崩れた文字になっている。左手でサラサラ書くには文字の形を崩すしかないからだ。どちらにしても左手ではきれいな文字を書けない。
右手と左手では、力の方向が違う。たとえば、左手ではかんたんなニンベンもサンズイも正しくは書けない。シンニュウなどは到底書けない。「月」や「刀」のかんたんなハライやハネも左手では書けない。結局、左手で書けるものは、漢字の代替品にしかならない。
文字をきれいに書けないと、自分の字に自信が持てないし、好きになれない。これは心理的にも社会的にも不利益になる。自分で書いたメモやノートも事務的に扱うだけで愛着をもてない。ビジネス場面でも自分の字を他人に見せたり、手書きで申請書や企画書を書いたり、履歴書を作成したりするときでも不利になる。
第二に、これは大事なことだが、左利きの人間は文字の代替品しか書けないので、ひらがなや漢字を書いても気持ちが楽しくなれない。漢字は一つ一つの字画の中に、気持ちがこもる仕組みになっていて、その仕組みに乗れるか乗れないかは大きな問題になる。
文字を書いて楽しめないことは、見過ごすことのできない欠陥で、書く楽しみから疎外されることは、毎日の生活の質に関わることだ。
文字を使って記録したり、感情を表現したり、深く思索したりするときに、文字に心がこもり滑らかに書ける楽しみがある場合と、ない場合とでは、生きる喜びの質が違ってくるのではないだろうか。
第三に、漢字の書字には、背景に書道という文化伝統がある。書道は漢字文化圏にしか存在しない世界に誇れる芸術だ。三千年の漢字の歴史に育まれた文化で、中国の六朝文化で盛んになり、日本にも導入され発展し、現在に至っている。
しかし、左手で漢字を書くことは、この書道文化から否応もなく断絶されることになる。左手でかろうじて漢字の代替品を書いていたのでは、書道にならない。右手で書いても本来の働き手でないほうを使うことになる。書道は絵画と違って、書かれた結果だけを見るのでなく、書く行為そのものも課題にしている。書く過程の精神統一のあり方が問題であり、書かれたものはその結果に過ぎないという考え方をする。書道は大胆さも繊細さも表現するが、その動作は槍投げの投擲のように、槍をより遠くに送るために全身全霊を手先に込める行為のようなものだ。
したがって、左手で漢字を書くことは、書道の伝統を享受することもできないし、継承、発展させることもできない。最初から書道文化に参加する機会を奪われている。小中学の習字や書道で、いやな思いをした左利きの人も少なくないだろう。
第四に、左利きの人間の書字行為がストレスの一因になり、様々な問題が社会的に指摘されている。日本ではじめて左利きの問題が社会的に提起されたのは七十年代で、左利きの子供と神経症の関係を調査した精神科医の研究だった。神経症のような精神障害になる子供のなかに、左利きの割合が多いことを指摘したものだ。
同様に発達障害や不登校、社会不適応、不活発な生活などがあげられる。原因は左利きに対するすべての社会的圧力が考えられるが、書字行為も確実な一因だろう。
この四つの問題は、それにもかかわらず、実際は無視されている。現実は左利きの人間は、右手を使ったり、左手を使ったりして、なんとか右文字の漢字を書いている。それは漢字の代用品に過ぎないけれど、それで日々をやり過ごしている。それで学校で学習し、会社で仕事をし、家庭で自分の生活や思いを記録している。とりあえず習慣で代替品を書き慣れているので、それでやむを得ずよしとしているのに過ぎない。本来は左利きの書道家も、右手で書を書かざるを得ない。
しかしこのやり方では、左利きの人間は、積極的な文字を書く喜びは得られない。なぜなら、脳科学で言う利き脳と利き手の働きと漢字システムの矛盾を、左利きの人間は解消できないからだ。現状でも代替品を作ることで代償行為的には解消できるかもしれないが、本来の文字を書く喜びを実感することはできない。