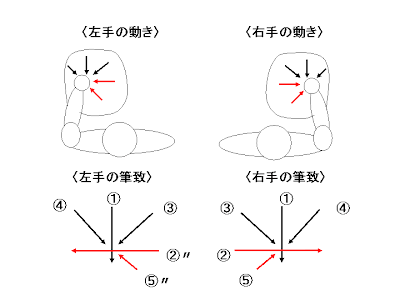これから、左文字を実際に書く練習をしていきます。ひらがなから、順に、カタカナ、数字、アルファベット、漢字と練習していきます。
その前に、われわれの目標を見定めておきます。単に左文字(鏡文字)をレタリングのように書けるだけでなく、左文字を日常生活の実用とすることを目指したい。
そこで、まず左文字のイメージをつかむためにいくつか例を示します。
右の詩歌を見ていただきたい。
①は、ご承知のように万葉集の有名な額田王の歌で、古代天皇たちのおおらかな恋の歌です。
②も、ご承知のように芭蕉の句で、字面からでも、林間に響く蝉の声が聞こえてきそうです。
③も有名な啄木の歌で、明治の清々しい叙情が言葉の表現から強く感じられます。
これら三つの歌はどれも文字の表面を見ただけで、すなおに歌の世界に引きつけられ、頭の中にその情景がありありと浮かんでくるのではないでしょうか。
では、次の詩歌はどうでしょうか。すぐに気付くでしょうが、反転してもまったく同じ歌です。
しかし、同じ歌だとは分かりながら、違和感が先に立ち、なんともいえない分かりにくさがあるのではないでしょうか。せっかくの歌の世界に浸りたくても感覚的に浸りきれないもどかしさが、あると思います。
左文字をはじめて見たときだれでも感じるところです。ほんとうに新しいものに触れたときは、たいてい眩暈(めまい)に似た途惑いがあるものですが、左文字も嫌悪に近い、途惑いがあるかも知れません。
何とも言えない違和感に圧倒されるところから、左文字の学習は始まると思います。
我々の最終目標ですが、今は違和感しか感じられないかも知れない左文字でも、いつかは見慣れて普通に感動できるようになることです。
左文字が容易に感じられるようになるまで慣れることによって、左文字で普通に生活できることを目標にしたいと思います。